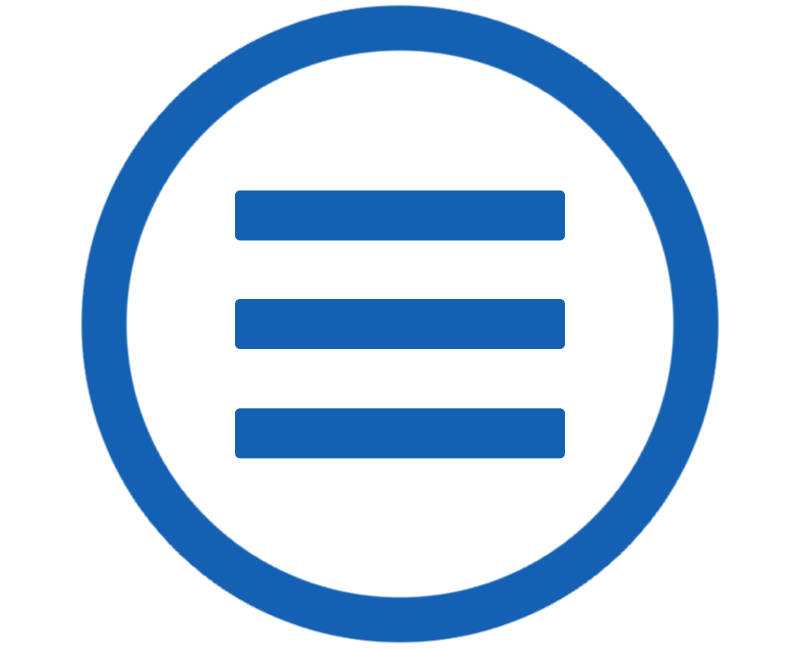
りゅーてつ日和!
これは、りゅーてつ好きが作った
りゅーてつ好きのためのサイト。
これは、りゅーてつ好きが作った
りゅーてつ好きのためのサイト。
流鉄それホント?
流鉄にまつわるそれホント?事案。
間違ったウワサが広まっていたりもします……
間違ったウワサが広まっていたりもします……
| ※まちがっていたらごめんなさい。 | |
| ▶ | 「流鉄」は本名? |
2008年から正式名称です。過去には流山軽便鉄道、流山鉄道、流山電気鉄道、流山電鉄、総武流山電鉄を名乗っていた時代がありました。これらの時代に地元で呼ばれていた愛称が「流鉄」で、愛称が正式名称となったかたちです。 地元でこの路線を呼ぶ場合は、この愛称から本名にまでなった「流鉄」のほか、過去の社名をもとにした流電や電鉄、また路線名である流山線などいう呼び方が主によく聞かれます。 逆に地元ではない方からすれば「流鉄」といういかにも愛称らしき名称が正式社名であるとは感じにくいようで、SNSやブログにはわざわざご丁寧に「流山電鉄(流鉄)」「流山鉄道(流鉄)」などと記載している投稿が多々あります。その括弧書きの中身が本名だぞ!と思いながら見ている流鉄ファンも多いことでしょう。 | |
| ▶ | 「りゅうてつ」アクセントは? |
A. 食堂 経験 郵便 銀行 B. 中国 現在 音声 ローソン 大きくわけて上記2種類があるかと思いますが、車内放送でも流れる公式のアクセントはAです。 常磐線各駅停車の車内で流れる自動放送はBとなっている点から、少なからずBのアクセントで読んでいる人もいるようですが、沿線では圧倒的にAが主流です。 | |
| ▶ | 日本イチ短い鉄道? |
流鉄が日本イチではありません。 事業者単位で、路面電車やモノレール等を除いたいわゆる「普通鉄道」だけでみると、独立路線(直通運転なしの路線)では日本で3番目に短い鉄道です(紀州鉄道、水間鉄道、流鉄)。他路線と直通運転しているものを含めると、5番目になります(芝山鉄道、紀州鉄道、横浜高速鉄道、水間鉄道、流鉄)。 | |
| ▶ | 日本イチ影が薄い? |
確かめようがありませんよね。そんなことをいわれて、このまちの人たちは喜ぶでしょうか。公共交通の使命は名前を売ることではなく、人やモノを運ぶこと。地域密着型で頑張っている交通機関は流鉄のほかにも全国にたくさんあるはずです。 | |
| ▶ | 都心から一番近い Suicaの使えない鉄道? |
距離的にみればこれは正解です。上野動物園内にあるモノレール(上野懸垂線)が2019年秋より休止となったため、都心から最も近い交通系ICカードの使用できない駅が流鉄の馬橋駅となりました。もっと厳密に言うとJRの馬橋駅ではSuicaが使えるため、「都心から一番近い、駅全体で交通系ICカードが使えない駅」というのは幸谷駅となるでしょうか。 | |
| ▶ | 現金以外はダメ? |
現金がないと列車に乗ることはできません。定期券・回数券の購入手段も現金のみで、クレジットカード・QUOカード・電子マネー・QRコード決済などなどその他手段は使用できません。窓口におけるグッズ類の購入も現金のみです。 ホーム上に電子マネー支払いが可能な自動販売機のある駅もあります。乗車の際にSuicaは使えませんが、飲み物はSuicaで買うことができます(笑) | |
| ▶ | 「都心から一番近いローカル線」? |
流鉄が公式に謳っているキャッチフレーズです。イベントの時に出されるのぼり旗にこの文言の記載があります。ホームページなどネット上には見当たらないのですが……。。。まわりのファンや利用者が言い出して広まったものではなく、自称したのが始まりです。最近は感染症拡大の影響でイベント開催も少なく、目にする機会は減りがちです。 | |
| ▶ | 流山市ではいちばん古い? |
現在の流山市域内では、市の右下をかすめるJR常磐線が最初です(1896年)。その次に東武野田線が開通しました(1911年)。1916年開業の流鉄は市内で3番目となります。 現在の松戸市域内では、常磐線に次ぐ2番目です。 | |
| ▶ | 西武鉄道と関係がある路線? |
流鉄の車両はかなり前から西武鉄道由来の譲渡車で統一されていることもあり、西武の関連路線と思われがちですが、特に資本関係はありません。 | |
| ▶ | 硬券がある? |
流山線は6駅すべてで厚紙状の「硬券」と呼ばれるかつて主流だったタイプのきっぷを発売しています。きっぷは片道・往復で購入が可能。入場券もあります。各駅ともに始発から終電まで窓口が開いているので、いつでも購入できます! | |
| ▶ | 延伸計画があった? |
会社設立直後から1960年代までの間に、流山から北方面と馬橋から南方面の両側に4度ずつ延伸の申請をだしています。 現在の路線図を見れば一目瞭然ですが、すべて実現していません。却下または申請取り下げによって、結果的に現在も開業時から変わらない馬橋~流山間です。 | |
| ▶ | かなり長い間、車庫に 停まったままの電車がいる……? |
自動車の車検に相当する検査(重要部検査および全般検査、4年に1度周期)は、台車や床下機器を外すなどと大がかりなため約1年ほどかかります。2両の編成が分割されて放置されているように見えたりもしますが、しっかり検査が行われています。しばらくしたら復活するので気長に待ちましょう。 | |
| ▶ | 「車掌さん」がいない? |
一般的な列車は前に乗る運転士と後ろに乗る車掌という2人の乗務員で運行されますが、流鉄では2010年より全列車がワンマン化し、車掌の乗務がなくなりました。車両最後部の乗務員室には誰も乗っていません。運転とドア開閉はどちらも運転士が行い、車内放送は自動化されています。 | |
| ▶ | とにかく「強い」? |
いちおう本当でしょうか。他会社線と比較して、降雪や荒天時の遅延または運転見合わせ率が低かったり、地震発生後の運転再開が早かったりするためこのように言われることがあります。 路線長が短く点検がしやすい、速度がそこまで早くないため遅れが発生しにくい、高い橋梁や高架区間がないために風の影響を受けにくいなどが考えられます。いずれにしても、異常時の対応の速さには頭が下がりますね。 | |
| ▶ | あまり人が乗っていない? |
地域密着型路線の現実を知りたいなら、平日朝の列車に乗ってみるべきです。確かに平日日中や休日夜間の乗客は少ない傾向にあります(つくばエクスプレス開業後は特に顕著ですよね)が、平日朝の流山線はしばしば座席の前に立ち客が出るほど混み合います。近年は観光路線へと舵を切りつつある流山線、まだまだ主となる任務は通勤通学輸送といえるでしょう。 | |
| ▶ | いつでも座れる? |
もちろんデータイムは座席に余裕があるものの、朝ラッシュ時の上り馬橋行は特に鰭ヶ崎や小金城趾といった途中駅からだと着席できません。「ローカル線」という文字列からは常に空いている閑散路線というイメージも受けますが、そんなことはありません。流山線は通勤通学輸送でも重要な役割を果たしています。 | |
| ▶ | 「町営鉄道」だった? |
「町民鉄道」と字面こそ似ていますが、似て非なるもの。これは誤りです。こう書くと、流山町という自治体が運営していたという意味になってしまいます。当時の流山町が流鉄を運営していたという事実はありません。 流鉄は流山町という自治体が運営していた公営の鉄道ではなく、当時の町の住民が主体となって設立し運営されていた純民間の私鉄です。(公営交通には「都営地下鉄」「鹿児島市電」「仙台市営バス」などがあります。) | |
