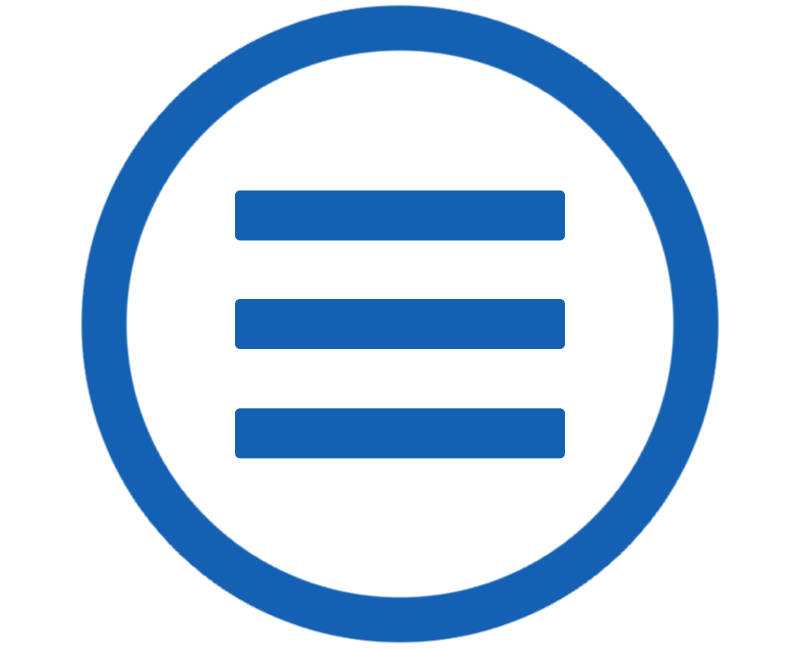
りゅーてつ日和!
これは、りゅーてつ好きが作った
りゅーてつ好きのためのサイト。
これは、りゅーてつ好きが作った
りゅーてつ好きのためのサイト。


流鉄沿線民が語る、流鉄のいろは。
わたしたちの日常は、こんな世界です。
わたしたちの日常は、こんな世界です。
流鉄って、こんなとこ。
| ※あくまで主観のおはなしです。 | ||
起点の馬橋から流山まで5.7km。最高速度は55km/hで、全線通しで約12分の旅です。開業当時は貨物輸送がメインでしたが、現在は旅客輸送のみとなりました。最近は観光にも力が入っています。短くても中身は濃いですよ! | ||
運賃の支払いは現金のみです!駅の窓口または券売機にてきっぷを買ったうえで乗車しましょう。券売機で使用できる紙幣は千円札のみなので、高額紙幣は窓口で両替が必要です。全駅、始発から終電までの全時間帯において駅員さんが常駐しています。 なお、ホーム上にある一部の飲料自動販売機では、SuicaやPASMOなどの電子マネーが使用できます。 | ||
厚紙状の「硬券」と呼ばれるタイプのきっぷが、いつでも窓口で買えます。通常の片道乗車券と入場券があります。 鋏痕(ハサミの形)はもちろん駅によって異なります。 | ||
券売機発行のきっぷには「入鋏省略」との表記があります。券売機できっぷを買ったらそのまま車内へ向かいましょう。 下車時は、改札できっぷを手渡しです。定期券・一日フリー乗車券は区間と日付をはっきりと提示しましょう。 | ||
馬橋・小金城趾・流山の3駅には、文字通り「ベル」が設置されています。Panasonic製の6型強力ベルという型式です。ジリジリという大きな音が聞こえてきたら、まもなく列車が発車します! | ||
酔いやすい方は注意……?車両の両端は特によく揺れます。走行区間の大半が江戸川沿いに広がる低地である、というのが関係しているかもしれません。 | ||
多少であれば発車を待ってくれます。各駅の駅員さんは、駅の周辺道路や階段の上を確認してから発車合図を出しています。もちろん油断せず急ぎましょう!! 夕方~夜にかけての時間帯では、馬橋駅で接続する常磐線各駅停車の到着に合わせて1分ほど発車を遅らせてくれることもあります。 | ||
一般的に、車両の前に乗って運転をする乗務員を「運転士」、後ろに乗ってドア扱いや安全確認を行う乗務員を「車掌」と呼びます。流鉄では運転士のみの「ワンマン運転」を行っているため、車掌は乗務していません(後ろ側の乗務員室には誰も乗っていません)。 | ||
電車はぜんぶで5種類!編成ごとに車体色が異なり、色に基づいた愛称が付けられています。1980年代より続く流鉄電車の伝統です。詳細は車両紹介のページで! 車両の正面についている、愛称が書かれた5角形のものは「愛称板」と呼びます。 | ||
ビル街から畑の中、スクランブル交差点やタヌキが住みつく林の脇まで。5.7kmにいろいろな風景が詰まっています。木製の架線柱や手書きの勾配標にも注目! | ||
時は明治の終わり、大量輸送手段が水上交通から陸上交通へ移りつつあったころ。水運の中継地として江戸時代から名を馳せていた流山でしたが、現在の常磐線が開通すると、町民はそちらを使うようになりました。しかし常磐線に乗るには、徒歩で片道1時間以上歩いて駅へ向かわなければなりません。そこで流山のまちの人々は有力者を中心に立ち上がり、資金を出し合い、馬橋駅から流山駅へ至る現在の流山線を開業させたのです(当時常磐線にあった駅は松戸・馬橋・北小金・柏でした。駅いちらんのページにある開業当時の周辺路線図も参照してください)。 このような歴史的経緯から「流山の人によってつくられた鉄道」という意味で、流鉄は「町民鉄道」であり、流山のまちの人々の誇りです。 | ||