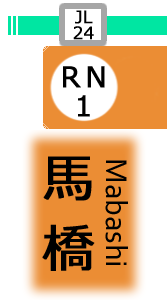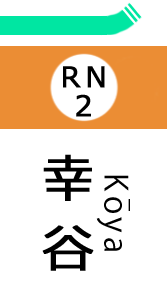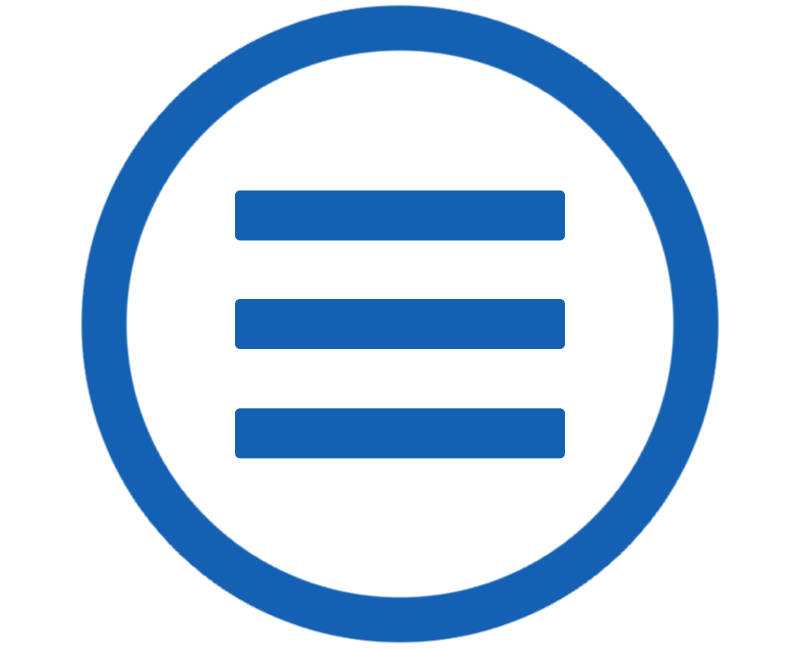
りゅーてつ日和!
これは、りゅーてつ好きが作った
りゅーてつ好きのためのサイト。
これは、りゅーてつ好きが作った
りゅーてつ好きのためのサイト。
馬橋駅
~街道と万満寺~
~レトロな旅への入口~
|
駅自体の開設は19世紀。現在の常磐線の馬橋駅として存在し、あとから流山線が乗り入れるかたちでした。 流山線の起点で、流山線ホームの南側には0キロポストがあります(ただし流山線ホームから見ることはできません)。 JRとの改札は別で、JRの改札は東西自由通路上の2階、流鉄の改札は自由通路から階段を下りた地上階にそれぞれあります。 |
諸データ
| ▶ 所在地 | 松戸市馬橋 |
| ▶ ホーム | 1面2線 |
| ▶ スロープ | × |
| ▶ エレベーター | × |
| ▶ 券売機 | 2台 |
| ▶ お手洗 | 改札内 |
| ▶ その他 | 待合室 |
えきまえ情報
| えきまえ情報 | |
| ▶ ロータリー | 東・西 |
| ▶ 公衆電話 | 東・西 |
| ▶ 郵便ポスト | 東 |
| ▶ コンビニ | すぐ |
年表
| 1896年、現在の常磐線が開通 (当初ここに駅はなし) | |
| 1898年、馬橋駅が開設 | |
| 1916- 3-14 | 流鉄開業 当時は常磐線と同じホームを使用 |
| 1971- 5-26 | 現在の流鉄専用ホーム使用開始 (常磐線の複々線化による) |
| 2011- 4- | 駅西側に馬橋ステーションモールが完成 |
| 2016- 7- | 新タイプの駅名看板が 他駅にさきがけ登場 |
| 2017- 3- | 券売機が新型に交換され、 流鉄からボタン式券売機消滅 |
| 2018- 4- | 駅ナンバリング導入 |
詳細情報
JRホームから見た流鉄の馬橋駅。間に常磐快速線の線路を挟むため、JR常磐緩行線のホームとは少々離れている。 後にそびえ建つ白い建物は2011年完成の"馬橋ステーションモール"。 |
ステーションモールから見た両線ホーム。ホームドア、柱の材質、屋根の形状、架線柱など、両ホームは並べるとなお雰囲気の差が際立つ。 |
常磐線をまたぐ自由通路の西側から。通路はJRの管理で、流山線の案内はかなり控えめ。途中に流山線ホームへ下りる階段がある。JRの改札は右奥。 乗換時間は2~3分ほどが標準だろうか。改札には「お願い 乗り換えの際、発車時刻が同時刻 または 相互に接近している電車は、接続できない場合がありますので、余裕のある電車をご利用くださいますよう お願いいたします。」という掲示がある。流山線は発車時に接続待ちをしてくれることがあるが、過剰な期待は禁物だ。通路を走り回るのも危険。 |
看板拡大。 |
階段を下りた先に流鉄の改札がある。ちなみにこの階段は右側通行。 流鉄の馬橋駅は橋上駅舎ではないものの、一度自由通路へ上がり、再度この階段を下りてホームへ向かう必要がある。 |
階段を下りて振り返ると、改札の正面に「JR線のりかえ」の案内看板が掲げられている。比較的新しめ。流鉄ホームから常磐線各駅停車への乗り換えは、階段を上って左折。 |
改札前。「自動券売機」という表示が誇らしい。自動改札やLED式の発車標がない流鉄では、このタッチパネル式券売機が旅客にとって最先端の電子機器かもしれない。 |
このサイトを見られている方は既にご存じだろうが、交通系ICカードは使えない。 Suicaをタッチする場所がないこと、またきっぷを買っても通す改札機がないことなどに戸惑う乗客を時たま見かける。 |
窓口の前に券売機が2台置かれている。当駅には流山線で最後までボタン式の券売機が設置されていたが、2017年3月にタッチパネル式へ交換された。 世相を反映し、2022年1月には券売機の脇に足踏み式のアルコール消毒液が置かれている。 |
改札前の柵には横断幕を掲出することがある。写真は大相撲の平成28年初場所で大関(当時)琴奨菊が初優勝を果たした時のもの(佐渡ヶ嶽部屋が松戸市内にあるため)。 |
改札ラッチには次の流山行の発車番線が掲示されている。ただし9割5分以上が1番線発車で、写真のような2番線発車という案内表示を見ることはめったにない。 次の流山行が2番線から発車する場合は、この表示に加え、構内アナウンスが入る。 |
改札ラッチの真上に設置されている白青ツートンカラーの看板。丸ゴシックがレトロさを醸し出す。 |
JRホームから見た改札の全景。明らかに常磐線の乗客を狙っているとわかる広告看板が屋根や柵に設置されている。 |
屋根は木造。ホームの南側(改札側)は白く塗装されている。 |
流山に向かって右が1番線、左が2番線。屋根の柱は両ホームの車両前に等間隔で並んでいる。 |
新タイプの駅名標が最初に登場したのは、ここ馬橋。木造屋根とのアンバランス感が伝わってくる。 設置されたのはナンバリング導入前で、導入後の現在は「RN1」がシールで貼られている。 |
ホームの奥、流山寄りには待合室がある。待合室の内部は板張りで、常磐線ホームの近代的な待合室とは全く雰囲気が異なる。 |
冷暖房完備で、夏季や冬季はかなりありがたい。ドア開閉は手動で、室内温度維持のためにも開けたらしっかり閉めよう。 |
待合室内にはアルコール消毒液が設置されている。世相を反映した感染症対策がしっかり行われている。 |
木造屋根からはレピーターもぶら下がっている。 |
馬橋駅ホーム一番の注目どころは、ホーム中ほどの自動販売機。一見何の変哲もない自販機だが、よく見ると電子マネーが使える。列車の運賃支払には使えないSuicaももちろん利用可能。 このようにホームの自販機でSuicaが使えるため、「流鉄でSuicaは使えない」というのは真っ赤なウソである(笑)。 |
基本は1番線を使用する。2番線には1編成が常駐しており、入れ替えがあるのは週に数回のみ。 |
馬橋駅2番線名物といえばこれ、「車両ドアの目の前に柱」である。停車位置の関係で、一部ドアの中央正面に屋根の柱が鎮座している。 車両と柱の間隔は開いているので、乗降に大きな支障はない。 |
2番線には車止めがある。 かつてはこの先へ続いていたようだ。 |
1番線の線路は、そのまま南へ延びる。この先でJRの線路と接続しており、新車両の導入時に使われる。その渡り線が最後に使われたのは5005編成"なの花"の入線時。 なお、これまでに引退した車両の搬出は流山駅からトレーラーに積み込むかたち(陸送)で行われている。 |
これが流鉄流山線の0kmポスト。 流鉄ホームからは残念ながらよく見えず、しっかり観察するには隣接するJRのホームへ行く必要がある。流鉄馬橋駅ホームからさらに200mほど南側に立っている。 |
流山線×常磐線 馬橋駅比較表
| 隣同士、どちらも1面2線。 同じ駅ですが、ちがいがたくさん。 | ||
| 流山線 | 常磐線 | |
| RN1 | 駅番号 | JL24 |
| ○ | 自動券売機 | ○ |
| ○ | 出札窓口 | × |
| ○ | 硬券 | × |
| × | 交通系ICカード | ○ |
| × | 自動改札 | ○ |
| ○ | 階段 | ○ |
| × | エスカレーター | ○ |
| × | エレベーター | ○ |
| ○ | トイレ | ○ |
| ○ | 待合室 | ○ |
| × | ホームドア | ○ |
| × | 自動放送 | ○ |
| × | LEDの電光掲示板 | ○ |
| 3両 | ホーム有効長 | 10両 |
| 2両 | 電車 | 10両 |
| × | 自動運転 | ○ |
| ○ | ワンマン運転 | ○ |
| ○ | 折り返し | × |